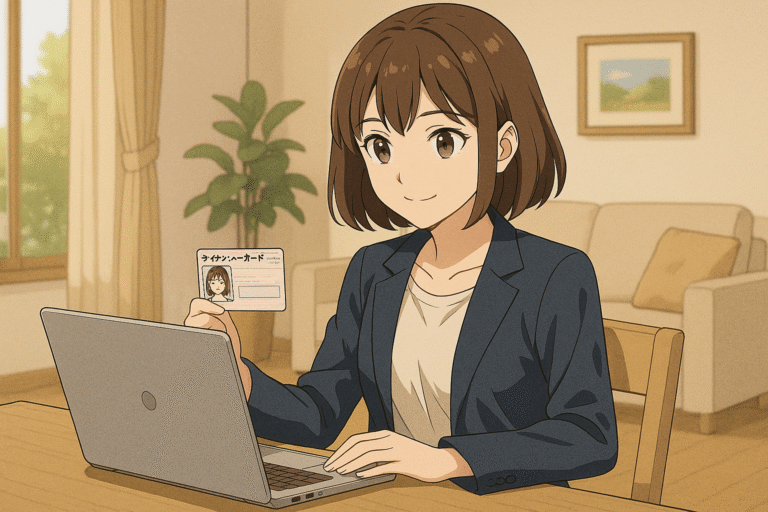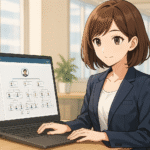2016年から全国で交付が始まったマイナンバーカードは、行政手続きの効率化やオンライン申請の普及に大きく貢献してきました。
しかし、発行開始から10年近くが経ち、技術の進化や社会のデジタル化に対応するため、政府は2028年にマイナンバーカードを全面刷新する方針を明らかにしています。
この刷新は、単なるデザイン変更ではありません。ICチップの暗号方式の強化やスマートフォン連携の拡充、さらには利便性とセキュリティの向上を目的とした、次世代カードへの大きなアップデートです。
背景には、デジタル庁が掲げる「誰もが安全・便利に行政サービスを利用できる社会」の実現があります。
この記事では、2028年の新カードで「何が変わるのか」、そして「今のカードはどうなるのか」を、利用者目線でわかりやすく解説します。
新カードで変わる主なポイント(2028年仕様に向けて)

2028年に登場する新しいマイナンバーカードは、見た目だけでなく、中身も大きく進化します。
目的は「より安全に」「より便利に」「より長く使える」カードへと進化させることです。
ここでは、刷新によって変わる主なポイントを紹介します。
新カードで変わる主な5つのポイント
まず、券面デザインと記載内容が見直されます。
現行カードでは表面にマイナンバー(個人番号)が印字されていますが、新カードではセキュリティ向上のため非表示化される方向で検討が進んでいます。
また、性別表記の削除など、プライバシーに配慮した設計になる見込みです。
次に、電子証明書と暗号技術の強化です。
従来の暗号方式をより安全な最新規格に切り替えるほか、有効期限を「5年」から「10年」へ延長する方向で調整されています。
これにより、更新の手間が減り、長期間安心して利用できるようになります。
さらに、暗証番号や認証アプリ(AP)の仕組みも改善予定です。複雑な暗証番号の入力に代わり、スマートフォンや指紋・顔認証を活用した生体認証によるログインの導入が検討されています。
これにより、高齢者やスマホ利用者でも使いやすくなります。
また、発行・更新体制の効率化も進められます。
現行カードと新カードの併存期間を設け、段階的に切り替える見通しで、2028年前後には新仕様へ完全移行する予定です。
自治体窓口での手続き負担も軽減されるよう、オンライン申請との連携強化が図られます。
最後に、利便性の向上です。
健康保険証機能、コンビニ交付、マイナポータル連携などのオンラインサービスがさらに拡充され、マイナンバーカード1枚でより多くの行政・民間手続きが完結できるようになります。
Audibleプレミアムプラン30日間無料体験2028年に刷新されるマイナンバーカードは、「安全性」「利便性」「長期利用性」を重視した大幅なアップデートとなります。下の表に主な変更点をまとめました。
| 項目 | 現行カード | 新カード(2028年~) | 変更の目的・メリット |
|---|---|---|---|
| 券面デザイン・記載事項 | マイナンバーと性別を印字 | 番号非表示・性別表記削除を検討 | プライバシーとセキュリティの強化 |
| 電子証明書・暗号技術 | 従来規格・有効期限5年 | 新暗号方式・有効期限10年へ | セキュリティ強化と更新負担の軽減 |
| 暗証番号・認証方式 | 暗証番号入力が必要 | 生体認証・スマホ認証を検討 | 利便性向上・高齢者にも使いやすく |
| 発行・更新体制 | 窓口中心・手続き多 | オンライン併用・段階的移行 | 発行効率化・自治体負担の軽減 |
| 機能・連携 | 行政中心(保険証・証明書交付など) | 行政+民間利用拡大・スマホ完結化 | デジタル社会での利活用促進 |
これらの変更により、新カードは「より安全・より便利・より長く使える」次世代の本人確認ツールへ進化します。
特に、マイナンバーの非表示化や生体認証の導入は、多くの利用者にとって大きな安心材料となるでしょう。
今のカード(現行仕様)はどうなる?利用者が知っておくべきこと
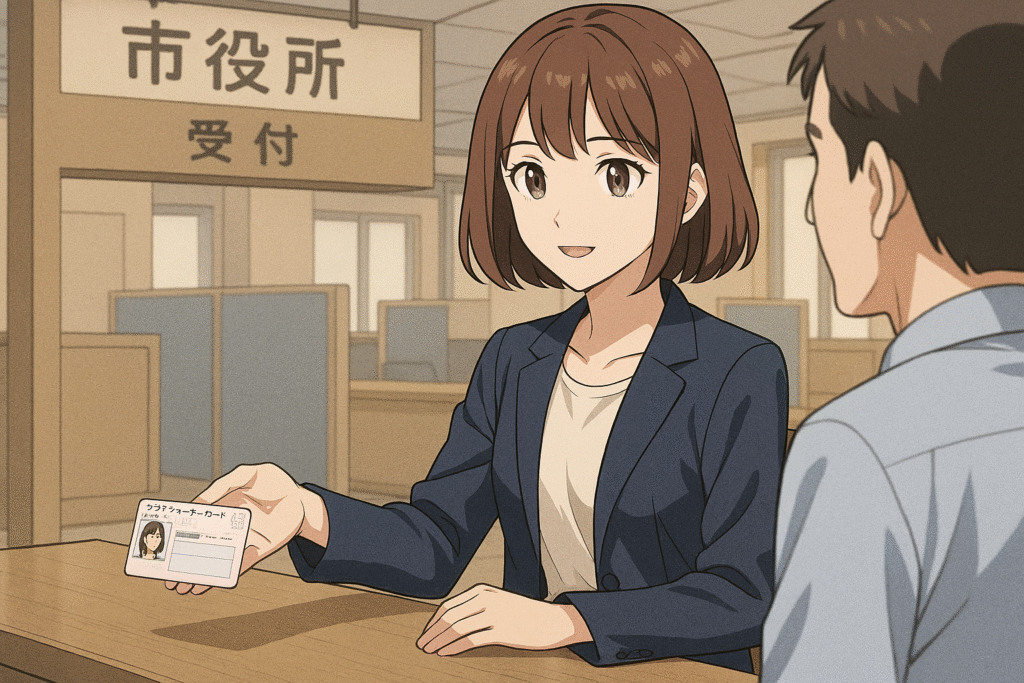
今のマイナンバーカードはどうなる?更新・切替えのポイントを整理

2028年に新カードが導入されても、現行のマイナンバーカードはすぐに使えなくなるわけではありません。
政府は段階的な移行を予定しており、現在のカードも有効期限内であれば引き続き利用できます。
ただし注意したいのが、電子証明書の有効期限です。
カード本体の有効期限(10年/未成年や有効期限切れ前更新などで異なる)とは別に、電子証明書の期限は原則5年です。
期限が切れると、マイナポータルや確定申告などオンライン手続きでの利用ができなくなります。
では、「更新を待つべきか」「今更新しておくべきか」はどう判断すればよいでしょうか?
電子証明書を頻繁に使う人(確定申告・健康保険証・公金受取口座登録など)は、今のうちに更新しておくのがおすすめです。
一方、利用頻度が少ない方は、期限内であれば新カード登場後に切り替える選択もできます。
手続きは自治体窓口で行えますが、混雑が予想されるため、更新時期を分散するのが賢明です。マイナンバーカードの更新通知が届いたら、早めの対応を心がけましょう。
以下の表で、利用者が知っておくべきポイントをまとめました。
| 項目 | 現行カードの扱い | 利用・更新のポイント |
|---|---|---|
| 有効期限 | 発行から10年間(未成年は5年) | 期限までは利用可。切替時期は段階的に設定される見込み |
| 電子証明書の期限 | 原則5年(カードとは別) | 期限切れ前に自治体窓口で更新が必要。切れたままだと電子申請不可 |
| 新カードとの併存期間 | 2026〜2028年頃に並行運用 | 移行期間中は旧カードも利用可。突然無効にはならない |
| 更新の判断基準 | 利用頻度に応じて判断 | 電子申請や保険証機能を使う人は早めの更新が安心 |
| 自治体窓口での手続き | 更新・再発行は窓口で申請 | 混雑を避けるため、通知が届いたら早めに行動を |
💡住民へのアドバイス
現行カードはまだしばらく使えますが、有効期限と電子証明書の期限は別物です。
特に電子証明書を使う人は、2028年の新カード導入を見据えて、計画的に更新しておくと安心です。
住民・事業者にとっての影響と対応ポイント
住民・事業者にとっての主な影響と対応ポイント

2028年のマイナンバーカード刷新は、利用者だけでなく自治体・企業にも大きな影響があります。
まず、住民にとっての変化です。
新カード導入により、コンビニ交付やオンライン申請などの手続きがよりスムーズになります。
たとえば、スマートフォンとの連携が進み、カードを読み取らなくても本人確認ができるようになる見込みです。
また、電子証明書の更新頻度が減り、煩雑な手続きが軽減される点もメリットといえます。
Audibleプレミアムプラン30日間無料体験一方で、高齢者やITに不慣れな方にとっては、操作方法の変化や新システムへの対応が負担となる可能性があります。
そのため自治体には、出張申請サポートやタブレット端末を使った申請支援など、住民に寄り添ったサポート体制の充実が求められます。
自治体職員としては、説明会や広報誌などを通じてわかりやすく案内することが大切です。
次に、事業者や自治体窓口側への影響です。
本人確認業務を行う企業や金融機関では、新カードのICチップや認証アプリ(AP)への対応が必要となります。
自治体も、窓口システムやカードリーダーの更新、セキュリティ設定の強化といった準備を進める必要があります。
最後に、今のうちに準備しておくべきこととして、現行カードの有効期限や電子証明書の更新時期を確認しておきましょう。
新カード切替え時に有効期限が近い場合、スムーズに移行できるよう余裕をもったスケジュール管理が重要です。
以下の表で、立場ごとの変化と対応ポイントを整理しました。
| 立場 | 主な変化・影響 | 対応ポイント |
|---|---|---|
| 住民(一般利用者) | コンビニ交付・オンライン申請がより簡単に。スマホ連携でカードレス化も進展 | 電子証明書の更新時期を確認し、切替時期を計画的に管理する |
| 高齢者・IT初心者 | 操作方法やシステム変更に戸惑う可能性 | 自治体の申請サポート・説明会・出張窓口を活用する |
| 事業者(本人確認を行う企業など) | 新ICチップ・暗号方式への対応が必要 | システムやカードリーダーを新仕様に対応させる |
| 自治体職員・窓口担当 | カード発行・更新システム、端末設定の更新が必要 | システム改修・職員研修・住民向け広報を早期に準備 |
| すべての利用者共通 | 新旧カードの併存期間中に手続きが集中する可能性 | 有効期限と電子証明書の更新タイミングを事前確認し、混雑を回避する |
💡ポイントまとめ
マイナンバーカードの刷新は、社会全体で進める「デジタル基盤の再構築」です。
利用者一人ひとりが正しい情報を把握し、自治体・企業と連携して円滑な移行を進めることが重要です。
まとめ:いつまでに何をすれば安心か?

マイナンバーカード刷新に向けて、住民が混乱しないよう「いつまでに何をすればいいか」を整理しておきましょう。
今回のカード刷新は、2028年をめどに本格導入される予定ですが、現行カードの有効期限までは引き続き利用可能です。
焦って更新する必要はありませんが、自分のカードの有効期限や電子証明書の更新時期を確認しておくことが大切です。
また、オンライン手続きや健康保険証としての利用など、マイナンバーカードを日常的に使っている人ほど、早めの準備が安心です。
自治体の窓口でもサポート体制が強化される見込みなので、不安がある場合は相談しておきましょう。
以下の表では、「今すぐやるべきこと」と「今後の準備」をわかりやすくまとめました。
Audibleプレミアムプラン30日間無料体験✅ いつまでに何をすれば安心?(利用者向けチェック表)
| 時期・段階 | やるべきこと | ポイント・注意事項 |
|---|---|---|
| 今すぐ(2025〜2026年) | マイナンバーカードの有効期限・電子証明書の期限を確認 | 有効期限はカード表面またはマイナポータルで確認可能 |
| 2026年頃 | 政府・自治体から発表される新カードの申請開始スケジュールを確認 | 旧カードでも当面利用可。急いで切替えなくてもOK |
| 2027年以降 | 新カード切替えの準備(更新手続きや申請方法を確認) | 生体認証・スマホ連携の有無をチェック |
| 2028年以降 | 新カードへの切替え完了を目指す | 切替え期限に余裕を持ち、自治体窓口が混雑する前に対応を |
💬 よくある質問(FAQ)
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q1. 今すぐカードを更新した方がいい? | 現行カードの有効期限までは利用可能。頻繁に電子申請する人は早めの更新を検討。 |
| Q2. 切替えには費用がかかる? | 通常の更新と同様、基本は無料(紛失・再発行時は一部手数料あり)。 |
| Q3. 手続きはどうやって行う? | 自治体窓口やマイナポータルでの申請が可能。今後はスマホ対応も拡大予定。 |
| Q4. 切替えをしないと罰則はある? | 罰則はなし。ただし、旧カードの電子証明書が切れると一部手続きが利用できなくなる。 |
マイナンバーカードの刷新は「突然使えなくなる」ものではなく、段階的な切替えが予定されています。
まずは自分のカードの有効期限をチェッし、必要に応じて電子証明書の更新を済ませておくことが第一歩です。
政府からの最新情報をフォローしつつ、2028年までに余裕をもって新カードへ移行できるよう準備しておけば安心です。
焦らず、正確な情報を確認しながら、マイナンバーカードを安心・安全に使い続けましょう。
参考・自治体からのお知らせ
マイナンバーカードの刷新に関する最新情報は、国や自治体の公式発表をもとに確認することが大切です。
特に「マイナンバーカード総合サイト」や「デジタル庁公式サイト」では、新カードの導入スケジュールや申請手続きに関する最新の動向が随時更新されています。
自治体によっては、独自のサポート窓口や相談会を設けている場合もあります。
更新通知が届いた際は、記載内容をよく確認し、有効期限・手続き方法・必要書類などをチェックしましょう。
疑問点があれば、記載されている自治体の窓口またはデジタル庁のコールセンターに問い合わせるのが確実です。
以下の表に、主な情報源と確認ポイントをまとめました。
🏛️ 参考・自治体からのお知らせ一覧
| 種別 | 主な情報源 | 内容・確認ポイント |
|---|---|---|
| 国の公式情報 | マイナンバーカード総合サイト | 新カード導入予定、更新手続き、FAQなどを随時更新 |
| デジタル庁公式サイト | https://digital.go.jp | 技術仕様・セキュリティ強化方針・カード刷新の全体像を公開 |
| 自治体公式サイト | 各市区町村のマイナンバー関連ページ | 発行・更新スケジュール、窓口対応時間、サポート窓口情報など |
| 通知書類・案内メール | 自治体からの封書やメール通知 | 有効期限・更新手続きの案内を必ず確認。期限切れに注意 |
| 問い合わせ先 | マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178 | 紛失・有効期限・電子証明書・更新方法などの相談対応 |
📅 今後のスケジュール目安
| 時期 | 主な予定・動き | 備考 |
|---|---|---|
| 2025〜2026年 | 新カード仕様の詳細公表・自治体準備開始 | 技術仕様・申請方法が段階的に発表予定 |
| 2027年 | 一部自治体で新カード先行発行開始 | 希望者への早期申請受付が始まる可能性あり |
| 2028年 | 新カードの全国導入 | 現行カードと併存期間を設け、順次切替えへ |
| 2029年以降 | 現行カードの段階的廃止・更新完了 | 有効期限切れを迎えた旧カードから順次更新へ |
マイナンバーカード刷新は国主導で進められるため、信頼できる情報源を確認することが何より重要です。
SNSなどで流れる非公式情報に惑わされず、必ず「マイナンバーカード総合サイト」や「デジタル庁公式サイト」、またはお住まいの自治体公式ページをチェックしましょう。
更新通知が届いたら、内容を確認して早めの対応を。手続きが集中する前に準備しておくことで、スムーズに新カードへ移行できます。